「焼いた鯖を骨抜きするとボロボロになってしまう」
「きれいに鯖の骨を取りたい!」
鯖の骨をひとつずつ骨を抜くと、身がボロボロになってしまいますよね。
先に結論をいうと鯖の身がボロボロにならないようにする使い方は、
- 中骨を中心に指で触りながらピンセットで骨を抜く
- まっすぐ抜かず斜めを意識して骨を抜く
上記の2つを意識するだけでも身がボロボロになりにくくなります。
今回は鯖の骨の取り方について紹介します。
ボロボロにならないような取り方、そもそもなぜ身がボロボロになってしまうのかも解説します。
ぜひ最後までお読みください!
なお、鯖の骨抜き用ピンセットは楽天でも販売されています。
滑り止め付きのピンセットは使いやすく握りやすいですよ。ぜひ覗いてみてくださいね。
鯖の骨抜きがボロボロになる!どうやって取る?骨の取り方を解説

鯖の骨抜きをするとボロボロになったら、どうやって取るのでしょうか?
鯖の骨をピンセットで抜く場合、中骨に注目し、指先で注意深く触りながら骨を抜きます。
中骨は太い骨が残っていることがあります。
鯖の身をできるだけ崩さないようにそっと取り除きましょう。
ちなみにピンセットを使わず骨を抜く方法もあります。
鯖の身を手でほぐすと小骨が見つかりやすいでしょう。中骨あたりを中心にして探すと見つかりやすいです。
骨を見つけたら指でそっと小骨を引き抜きましょう。
余談ですが骨取り鯖を選べば、焼いた後に骨をひとつずつ取らなくても食べられるので時短に便利です。
美味しい鯖をまとめ買いできるのでぜひ検討してみてくださいね!
鯖の骨抜きがボロボロにならないコツはある?
鯖の骨抜きがボロボロにならないコツは4つあります。
1.鯖の骨には角度がある

鯖の骨抜きで身がボロボロにならないコツとして、あらかじめ鯖の骨の角度をイメージするとよいでしょう。
小骨は斜めになっているため、角度を意識せずにまっすぐに引き抜くと身が崩れてしまうおそれがあります。
骨抜きなどで骨を引き抜く際、やや斜め方向を意識すると抜きやすいです。
2. 身のスジに注目する

鯖の身にあるスジに注目しましょう。スジは骨がどのへんにあるのか目安になります。
鯖の身を触りながら骨抜きを行うと、より正確に骨を取り除くことができます。
腹骨や背骨の部分はスジがはっきりしているため、目印にしやすいです。
3. 骨抜き用のピンセットを使う

鯖の骨抜きをする場合、専用のピンセットを使用するとよいでしょう。
魚の骨抜き専用のピンセットはより細かい骨をしっかりと掴めます。
ピンセットを使う際は力を入れずに優しく骨をつまむことがポイントです。
ピンセットには関東派と関西派があります。アジやイワシなどの身が柔らかい魚は関東派、鯖などの血合いが多い魚は関西派を使いましょう。
4. 骨抜きの手順を守る

鯖の骨抜きには手順があり、しっかりと守ると身がボロボロになりにくいです。
鯖をしっかりと押さえ、骨の位置を確認しながら頭側から尾側に向かって骨を引き抜くようにします。
骨の骨抜きがボロボロになる原因は?
なぜ骨抜きがボロボロになってしまうのでしょうか?その原因を2つ挙げてみます。
1. 骨を抜くタイミングが悪い

骨を抜くタイミングが悪いと、身が崩れてしまうことがあります。
たとえば冷凍の鯖を解凍していない状態で骨を抜こうとするとうまく抜けないことがあります。
適度に常温に戻してから骨抜きを行うと、スムーズに作業が進みます。
2. 骨抜き用に適した道具ではない

骨抜きに適した道具を使っていない場合は、鯖の身はボロボロになってしまいます。
骨抜き用のピンセットの見た目が毛抜き用のピンセットと似ていて代用に使える場合もあります。
しかし、骨抜き用のピンセットは100均でも販売されているので、せっかくなら骨抜き用のピンセットを使ったほうが使いやすいでしょう。
魚専用の骨抜き道具を使えば、効果的かつきれいに骨を取り除くことができます。
まとめ:鯖の骨抜きがボロボロ!どうやって取るのかコツを紹介
鯖の骨抜きは、コツを押さえることで、身がボロボロになりにくいです。
骨の角度を意識し、魚の身のスジを目印に専用のピンセットを使い、手順を守ることが大切です。
コツを暗記して実践すればきれいに骨を抜くことができ、見た目はもちろん食べても美味しい鯖が味わえるでしょう!
ちなみに美味しい鯖にはご飯が欠かせません。
象印の圧力IH炊飯器ジャー「極め炊き」についての記事も合わせてお読みくださいね。
合わせて読みたい:【旧型と比較】象印の圧力IH炊飯器ジャー極め炊きNP-RU05の特徴3つ!NT-RT05との違いも
炊飯器を変えるだけでご飯の美味しさも変わりるので、この記事を機に検討してみるとよいかもしれません!
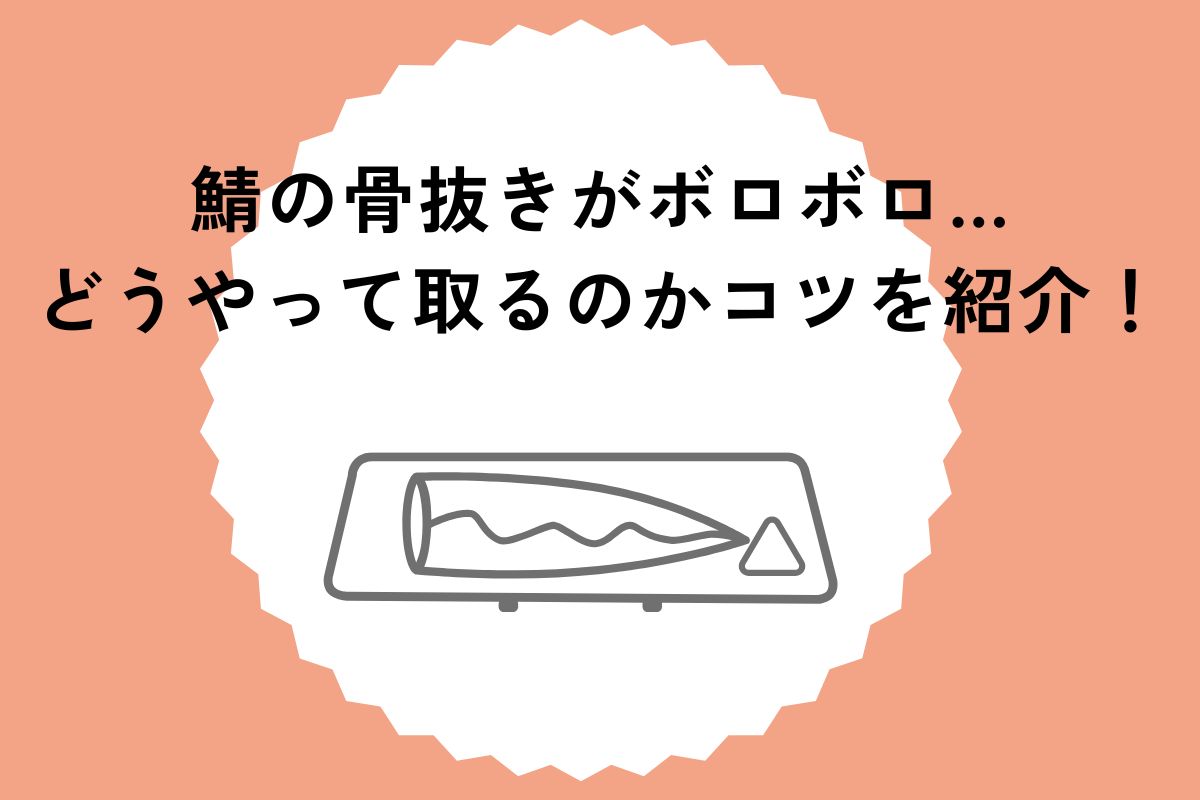





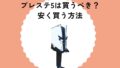
コメント